掛け払い比較について
公開日: ( 最終更新日: )
目次
掛け払いとは
企業に事業用の商品やサービスを販売する際、代金を後日一括で支払ってもらう決済方式のことです。具体的な流れは以下の通りです。
- 企業から商品やサービスの購入を受け付ける
- 販売企業は、購入企業の与信審査を行う
- 与信が認められれば、販売企業は商品を引き渡す
- 購入企業から、後日一括で代金を支払ってもらう
販売から支払いまでの期間は30日~60日程度が一般的です。
購入企業にとってのメリットは以下の通りです。
- 購入時に資金が不要なため、キャッシュフローを改善できる
一方で、販売企業側のメリットは以下の通りです。
- 上述した購入企業にとってのメリットによって、新規顧客との取引開始が容易になる
- 販売機会が増え、売り上げアップが期待できる
掛け払いは、企業間取引(BtoB)で最も多く利用されていています。ただし、代金回収リスクが高まることから、販売企業は購入企業の審査を厳格に行う必要があります。
また、支払い遅延や未払い案件などが発生した場合には督促回収業務の手間も増えます。
近年ではそのデメリットをカバーすることに特化した掛け払い決済代行サービスが増えてきています。
掛け払い決済代行サービスの選び方を目的別に解説
掛け払い決済代行サービスを販売企業の視点から目的別に選ぶポイントの一例をご紹介します。
【代金回収リスク回避が目的の場合】
- 未払い保証のある決済会社
- 決済手数料率が低い決済会社
まずは、未払い保証のある決済会社を選ぶべきです。購入企業の支払いが遅れたり、未回収が発生した場合も決済会社が全て保証してくれますので安心して取引できます。
続いて決済手数料です。未払い保証を利用するための決済手数料が、実際の未払い額よりも大幅に増えてしまっては本末転倒だからです。
自社完結で掛け払いをした場合の未払い率、未払い金額、それに対応する人件費などの管理費を試算して、決済代行サービスの費用と比べてみましょう。
注意してほしい点は、上記2点だけで選ばないということです。保証がついて決済手数料が低くても、与信審査が通らなかったり、与信枠が足りなければ機能しない決済サービスとなってしまいます。
以降で解説するポイントも参考にして、総合的に判断してください。
【売り上げ拡大が目的の場合】
- 購入企業に対し、販売企業が希望する与信枠を出せる決済会社
- 購入企業が希望する支払いサイクルに調整できる決済会社
購入企業に、希望する与信枠を提供できるかどうか重要なポイントになります。
毎月100万円の取引があるのに対して与信枠が40万円しか出なければ、掛け払い決済代行サービスは使いものになりません。
支払いサイクルも忘れずにチェックしたいポイントです。
業種業界によっては特殊なビジネスルールがある場合があります。支払いサイクルが、45日が一般的という業界の場合には、決済代行サービスの一般的な30日サイクルでなく45日への変更対応ができるかどうかが購入企業の使い勝手に大きく関わってきます。
注意してほしい点は、与信枠の適用モデルです。
購入企業の与信枠を販売企業が独占できるモデルは、月100万円の与信枠の場合100万円まで取引できます。購入企業が、他販売企業とどれだけ取引しても与信枠に影響はありません。
購入企業の与信枠を複数の販売企業で共有するモデルだと、月100万円の与信枠でも既に他販売企業で70万円の取引をしている場合、30万円の与信枠しか残っていないことになります。
与信枠や支払いサイクルだけでなく、与信枠が適用される範囲も含めて判断してください。
【請求管理業務の軽減が目的の場合】
- アウトソースできる業務が多い決済会社
- 決済代行サービスの運用負担が少ない決済会社
請求管理業務のどこまでをアウトソースできるのかは、販売企業の業務軽減に大きく影響します。
全て社内完結で行うと社内与信・請求・回収・入金確認・督促・消込・問合せ対応等のたくさんの業務が発生しますが、これら全てをアウトソースできる決済代行サービスもあります。
さらに決済代行サービス導入後の運用負担を抑えられるよう、システム化が進んでいる決済会社を選ぶとよいでしょう。取引審査の登録や審査結果の受取が、人手を介さずプログラムで全自動処理できるAPIで対応できると、とても効率的です。
このように、売り手企業の目的に応じて、重視するポイントは変わってきます。トータルで最適な決済会社を選ぶためには、自社の経営方針やビジネスモデルに合わせて検討することが不可欠です。
掛け払い決済代行サービスの特徴
各社の特徴を解説します
Paid(ペイド)

Paidの特徴
- 購入企業には、他決済代行サービスよりも大きな与信枠が設定されています。
- 購入企業の与信審査の際、稀にPaidから購入企業へ電話による確認が入る場合がありますが、それによって与信枠が0円となる事態を避けることが出来ています。
- SaaSビジネスのような定額課金サービスに最適化された定額自動請求システムも提供。毎月の請求プロセスを簡素化し、効率的な収益管理を実現することができます。
Paidの費用
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 0円~ ※要見積 |
| 決済手数料 | 取引金額×0.5~3.1%(非課税)※要見積 |
| 請求書発行費用 | 125円(非課税) ※コンビニで支払う際は、購入企業に下記費用が別途掛かります。 10,000円未満:66円~110円 10,000円~50,000円未満:110円~220円 50,000円~300,000円:330円~550円 |
NP掛け払い

NP掛け払いの特徴
- 販売企業が購入企業の与信枠と利用状況を把握しやすいシステムなので取引管理が簡単です。
- 通信販売、営業販売、SaaSなどの月額課金、さまざまなビジネスモデルに対応できるよう、サービスの仕様が柔軟に変更できる設計になっているので運営が容易です。
- NP掛け払いのバックオフィスの人員体制が手厚く、きめ細かいサポートと対応を行ってくれます。
NP掛け払いの費用
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 12,000円~ ※要見積 |
| 決済手数料 | 取引金額×1.2~3.6% ※要見積 【決済手数料内訳】 債権買取手数料(非課税) 0.2~0.5% システム利用料(課税・税別)1.0~3.1% |
| 請求書発行費用 | 1通あたり0円~252円 |
〈請求書発行費用 詳細〉
電子メール請求:0円
請求書郵送(銀行振込):177円
請求書郵送(銀行振込・コンビニ):252円
口座振替:メール90円、郵送217円
※非課税表記以外は、税抜表記
マネーフォワード掛け払い

マネーフォワード掛け払いの特徴
- 販売企業のシステムにAPIやWebhookを組み込むことで、きめ細かいカスタマイズ開発が可能な基盤を持っています。
- 多くの高度な機能を備えながらも、決済手数料は低く抑えられています。
- 購入企業ごとに、支払期日を柔軟に設定することができます。
- 早期払いオプションや、保証なしの請求代行のみのサービスなど、様々なオプションサービスを充実させており且つ使いやすい設計になっています。
マネーフォワード掛け払いの費用
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 0円~ ※要見積 |
| 決済手数料 | 取引金額の0.5~3.5%(非課税) ※要見積 |
| 請求書発行費用 | 1通あたり0円~380円 |
〈請求書発行費用 詳細〉
請求書郵送費用:215円/通
※コンビニ支払い時+165円
PDF(メール):0円
※非課税表記以外は、税抜表記
RP掛け払い

RP掛け払いの特徴
- 都度発生する商取引を一定期間でまとめて請求し、一括で代金回収を行う、BtoB向けの企業間決済代行サービスです。早期払いオプションを利用すれば、締日から最短5営業日で入金も可能。
- 与信審査を通過した債権は100%保証されます。与信NGの自社債権も同システム上で債権管理が可能です。該当企業への請求を自動で行い、入金管理も可能。
- 定期的な支払いが発生するサブスクリプション型のビジネスモデルと相性が良いです。一方で、通常のECサイト(オンラインショップ)には適していません。
- クレジットカード決済と「RP掛け払い」を併用したい場合、このシステムが効果的です。複数の支払い方法を提供したい企業にとって便利な選択肢となります。
RP掛け払いの費用
| 初期費用 | 300,000円(税抜)※要見積 ※3ヶ月の専属サポート(オンボーティング)費用含む |
| 月額費用 | 50,000円~ 請求件数によって変動 ※要見積 |
| 決済手数料 | 取引金額の0.5~3.4% ※要見積 |
| 請求書発行費用 | 0円(月額費用に内包) |
GMO掛け払い
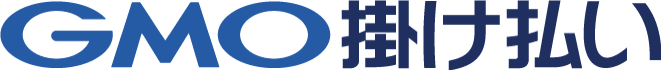
GMO掛け払いの特徴
- 非常に大きな与信枠を提供できます。数千万円以上の高額な取引にも対応可能なため、大規模な企業間取引に適しています。
- サービスには多様な機能やオプションが用意されています。
ただし、GMO掛け払いのこれらを効果的に活用するには、決済システムに関する高度な知識と経験が必要となり扱うのが難しいです。 - 与信(信用取引の限度額)を設定する際、購入側の企業に求める情報が他社のサービスと比べて多くなっています。これは、より詳細な審査を行うためです。
GMO掛け払いの費用
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 0円~14,000円(税抜) ※要見積 |
| 決済手数料 | 取引金額の0.5%~3.4%(非課税) ※要見積 |
| 請求書発行費用 | 1通あたり0円~242円 (税抜) |
〈請求書発行費用 詳細〉
請求書郵送費用:ハガキ208円/通、封書242円/通
PDF(メール):0円
※非課税表記以外は、税抜表記
クロネコ掛け払い

クロネコ掛け払いの特徴
- ヤマト運輸の配送サービスを使って企業間取引を行う場合、「クロネコ掛け払い」というサービスが利用できます。
- この支払い方法では、商品を購入する側の企業に与信枠(後払いできる限度額)が設定されます。
- 初めて取引を行う企業でも、最初から60万円分の与信枠が2ヶ月間提供されます。これにより、予想以上に小さな与信枠が設定されて困るといった問題が起こりません。
クロネコ掛け払いの費用
| 初期費用 | 0円 |
| 手数料 | 取引金額の2.0~5.0%(非課税) ※要見積 |
| 月額費用 | 0~10,000円(税抜) ※要見積 |
| 請求書発行費用 | 0円 ※ただしコンビニで支払う際は、買い手企業に下記手数料が別途掛かります。 10,000円未満:110円 10,000円~50,000円未満:220円 50,000円~300,000円:セブンイレブン440円、 ローソン・ファミリーマートなど550円 |
よくある質問
Q. 掛け払いと他決済の違いはなんですか?
A. 掛け払いとは下記を満たす支払い方法です。
- 販売企業は購入企業を信用して、先に商品を引き渡す
- 購入企業は商品を先に受け取り、後日一括で代金を支払う
- クレジットカード会社は関与しない
その他の主な決済方法
- 前払い
- 現金支払い
- クレジットカード決済
- ローン契約
掛け払いは販売企業と購入企業の相互の信用関係に基づく決済方法です。
他の決済と比べ、購入企業は支払いを後回しにできる半面、販売企業は代金回収リスクを抱えます。
そのデメリットをカバーすることに特化した掛け払い決済代行サービスを本章ではご紹介しています。







