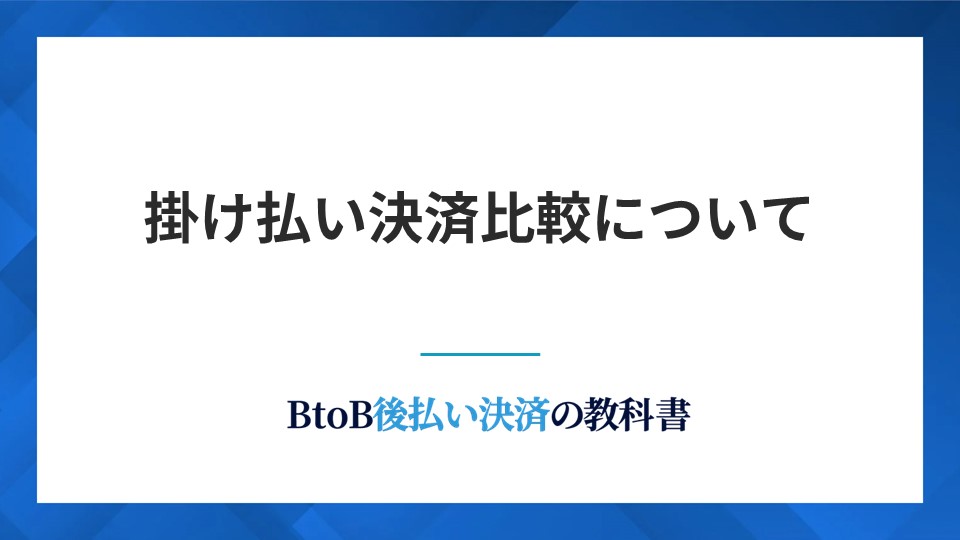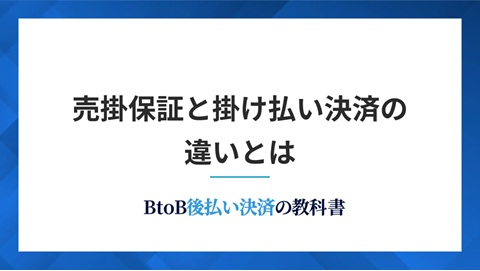請求代行と掛け払い決済代行の違いとは?
公開日: ( 最終更新日: )
目次
はじめに
取引先が多い企業では、請求書の発行から代金回収や入金消込まで、膨大な業務量とそれに伴う未回収リスクが経営上の重要な要素となっています。
この課題を解決するサービスとして「請求代行」と「掛け払い決済」が注目されていますが、名称が似ているため混同されがちです。しかし、両サービスはアウトソースできる業務範囲と未回収リスクにおいて根本的に異なる特徴を持っています。
本コラムでは、両サービスの違いを分かりやすく解説します。
請求代行は「業務効率化に特化したアウトソーシング」
サービス概要
請求代行は、請求書の作成・発送といった請求業務を専門会社に委託するサービスです。「請求業務のアウトソーシング」と捉えるのが最も適切でしょう。
アウトソースできる主な業務
- 請求書の作成・発行:取引データを基に請求書を自動生成
- 請求書の送付:郵送・メール・FAXによる配送業務
- 督促業務:支払期日を過ぎた場合のリマインド業務(オプション)
重要な特徴:未回収リスクは、自社が負担
請求代行で最も重要なポイントは、売掛金の回収責任と未回収リスクが自社に残ることです。代行会社は請求業務の処理を行いますが、取引先が支払いを行わない場合の損失は、自社が負担することになります。
料金体系
- 請求書1通あたりの単価制:50円~200円程度
- 月額固定費制:月額数万円~数十万円
- 初期導入費用:システム連携費用として数十万円程度
会計計上の方法
請求代行を利用しても、経理処理の基本構造は変わりません。
- 売掛金は取引先に対して通常通り計上
- 代行手数料は販売費及び一般管理費で処理
- 入金管理と貸し倒れリスク管理は継続して必要
掛け払い決済は「債権譲渡によるリスク回避を含む経営ソリューション」
サービス概要
掛け払い決済は、決済代行会社が売主と買主の間に介入し、与信判定から請求や回収まで決済業務全体を代行するサービスです。代金回収の保証が提供されることが大きなポイントです。
主な業務内容
- 与信審査:取引先の支払い能力を事前に審査
- 請求業務:請求書の作成・発行・送付
- 代金回収:取引先からの入金管理
- 督促・債権回収:未払い時の督促から法的手続きまで
- 貸し倒れ保証:取引先の支払い有無に関わらず入金まで保証
重要な特徴:未回収リスクは、決済代行会社が負担
掛け払い決済の最大の特徴は、未回収リスクが決済代行会社に移転する点です。取引先が倒産や支払い不能に陥った場合でも、契約企業は決済代行会社から確実に代金を回収できます。督促業務なども一切必要ありません。
料金体系
- 売上連動の手数料制:売上高の1~3%程度
- 初期費用・月額固定費:0~数万円(多くの場合は数千円程度)
- 請求書発行費用:0~約400円/社(郵送/メール、コンビニ支払い可否によって異なる)
会計計上の方法
掛け払い決済では、決済フローが大きく変わります。
- 売掛金の相手先が決済代行会社となる
- 決済手数料は売上高から控除または販売費で処理
- 貸し倒れリスクが実質的に消失
両サービスの比較:どちらを選ぶべきか
比較表
| 比較ポイント | 請求代行 | 掛け払い決済 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 業務効率化 | 業務効率化 + リスク移転 |
| 回収リスク | 自社が負担 | 代行会社が負担 |
| 債権の帰属 | 自社が保持 | 代行会社に移転 |
| 業務範囲 | 請求業務のみ | 与信~回収まで全般 |
| コスト構造 | 固定費中心 | 売上連動の変動費 |
| 取引関係 | 既存関係を維持 | 代行会社が介入 |
請求代行が適している企業
こんな企業におすすめ
- 請求業務の効率化が課題
- 取引先との直接的なキャッシュフロー関係を重視
- 信用リスクは自社で管理したい
- コストを最小限に抑えたい
- 既存の与信管理体制が確立されている
具体的なケース
- 長年の取引実績がある安定した顧客が中心
- 社内に信用管理部門がある
- 請求書発行業務の人的コストが課題
掛け払い決済が適している企業
こんな企業におすすめ
- 業務効率化と同時に未回収リスク軽減も図りたい
- 新規取引先の開拓を積極的に行いたい
- 信用リスク管理のノウハウが不足している
- キャッシュフローの改善を重視
- 売上連動のコスト構造を受け入れられる
具体的なケース
- 新規事業や新市場への参入を検討
- 中小企業との取引が多い
- 貸し倒れ実績があり、リスク軽減が急務
- 与信管理の専門人材が不足
- EC卸(BtoB-EC)を立ち上げ、決済手段に請求書支払いを搭載したい
まとめ
請求代行と掛け払い決済は、いずれも企業の請求業務効率化に貢献するサービスですが、その性格は大きく異なります。
請求代行は「業務のアウトソーシング」として、コストを抑えつつ業務効率化を図りたい企業に適しています。一方、掛け払い決済は「リスクも含めた決済機能の外注」として、業務効率化と同時に信用リスクからの解放を求める企業に適しています。
取引先の信用力、社内リソースの状況、コスト構造の許容度などを総合的に勘案し、自社にとって最適なソリューションを選択することが重要です。
どちらのサービスも、適切に活用すれば企業の競争力向上に大きく貢献するツールとなるでしょう。まずは自社の現状を正確に把握し、課題の優先順位を明確にした上で、サービス選択を検討することをお勧めします。